| 鉄の過去 | |
| 鉄の過去のブログ | |
| 年代 | 30代後半 |
|---|---|
| 性別 | 男性 |
ブログライター
ブログ
| TITLE. 【コラム】ゲーム研究の記念碑的名著『ハーフリアル』は、なぜ邦訳に10年要したのか |
DATE. 2016年10月21日 19:23:07 |
THEME. 未分類 |
|
ゲームとはなにか――読者の多くはこの問いを持ち、それぞれ自分なりに答えを出した経験があるのではないでしょうか。もう少し思索を続けて、「ゲームはフィクションなのか、リアルなのか」「〇〇なんてゲームとはいえない、と言うとき、なぜそれはゲームとはいえないのか」「ゲームにおける”物語”とはなにか」といったことを考えたこともあるかもしれません。
イェスパー・ユール著『Half-Real(ハーフリアル)』は、”ゲーム研究の記念碑的名著”として紹介されている本です。2005年の文章ですが、2016年の9月、翻訳され日本語版が発売となりました。本書の訳者でありゲーム研究者である松永伸司氏によれば「人文系ビデオゲーム研究の古典的な研究書」。上記のような問いに答えを出してくれるかもしれません。
これまでの「(ビデオゲームでない)ゲーム」の歴史も汲んでおり、こういった本を読んだことがない、という人にとっての入門書としての機能も果たしてくれます。作者のユールによれば、ビデオゲーム研究が分野としてまとまりを持ち始めたのは2000年前後とのこと。20年弱という短い歴史しかない中で、周辺の分野を援用しながら研究は行われてきました。本書も多数の参照を行なっており、ゲーム研究概論として読むこともできます。
個別のゲームに関する膨大なテキストと比して、総体としての「ビデオゲーム」についてのテキストが極めて少ない、日本ではこうした状況が続いています。ときおり硬質な文章が出てきても、それは個別の対象に対しての「テクノロジー」としてのゲームだったり、「ビジネス」としてのゲームについてのものだったりします。また比較的多く出ている「ゲーム史」についての文章でも、「ゲームとはなにか」は自明のものとして看過されることが多いです。現状もっともゲーム研究に近いのは、作り手に対して書かれるゲームデザイン関連です。
ユーザーレベルでも、ビジネスとしてのゲームについてアナリストさながらに語る人、ゲームハードの構成や特定のゲームソフトの品質について用語を駆使して語る人、個別のゲームについて作者以上に知識を有する人は少なくありません。しかし、ゲームそのものについて語る人はそう多くありません。
翻訳されて日本で発売されるまで10年超、そして出版を行うのがボードゲーム販売を手がけている会社(ニューゲームズオーダー)である――このことからも、日本で「ビデオゲーム研究」という分野がビデオゲーム全体の中で見逃されてきたことがうかがえます。私自身においても、この本との出会いは「Amazonのおすすめ商品」に並んでいたからにすぎません。
日本のビデオゲームは、『スペースインベーダー』や「ファミコン」で世間から認知されはじめたときから「アヤしげなもの」「こどものおもちゃ」という印象を持たれていました。そこでゲームについて語るとき、ある意味で”不真面目に”語ることが適当であり、真面目な考察は「小難しいことを語っちゃって」と揶揄される風潮がありました。ゲームが進歩した今でも「ギークと青臭い男子の文化が持つ低俗さの一覧表だと思われている」(『Half-Real』から引用)」部分は否めません。「シネフィル」や「本の虫」に比べて「ゲーマー」という響きが否定的なニュアンスを持ち続けているのも事実です。
また「たかがゲーム」「ゲームなんてひまつぶし」といった声がいつの時代もあります。他のジャンルでもそういった声はいくらでもありますが、問題なのは、ゲームをプレイするユーザー自身も、そういった考えを持ちながらプレイしている場合がある、という点です。
どういうことかというと、たかがゲームと考えていたり、ひまつぶしでゲームをしている人が「ゲーム研究」という分野に興味を持つのか、ということです。「たかがゲームを”研究”するなんて」と冷笑されてしまうか、無視されてしまうか。これは「プロゲーマー」や「eスポーツ」への視線と近いものがあります(世界的に見て日本は、ゲーム自体の先進性と比べるとeスポーツが普及していません)。
タイトルの『ハーフリアル』は、ビデオゲームがふたつの異なる側面を同時に持つものであるということを表している。ビデオゲームは、プレイヤーが実際にやりとりする現実のルールからなるという点で、またゲームの勝敗が現実の出来事であるという点で、現実的(real)なものだ。一方で、ドラゴンを倒すことでゲームをクリアするという場合、そのドラゴンは現実のドラゴンではなく虚構的(fictional)なドラゴンだ。そういうわけで、ビデオゲームをプレイすることは、現実のルールとやりとりすることであると同時に、虚構世界を想像することでもある。そして、ひとつのビデオゲーム作品は、ひとまとまりのルールであると同時にひとつの虚構世界でもある。(『Half-Real』冒頭から引用)
|
||

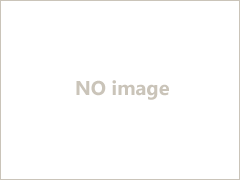

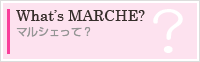
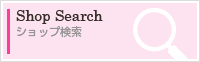

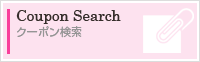
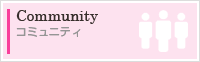
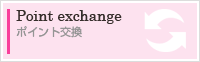
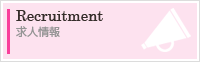



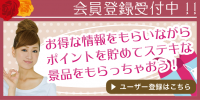


コメント
コメント:0件
コメントはまだありません